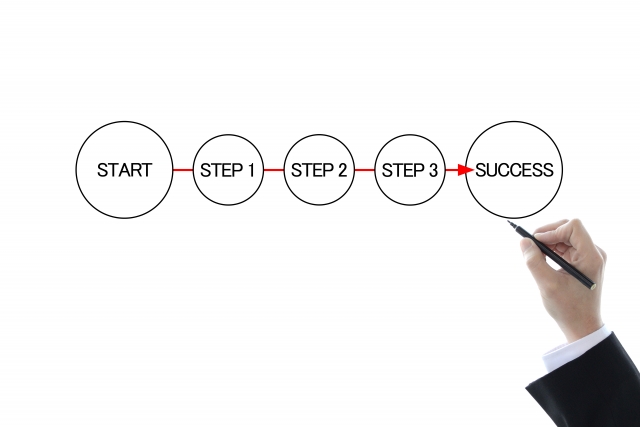
こんにちは!
コロナの影響も段階的な解除が進んで職場に戻っている方もおおいのではないでしょうか?
4月から入社する予定だった人も数日出勤して休業と新社会人として戸惑いながら生活している事と思います。
今回はアラフォーおっさんが色々とサラリーマンをしていてまず先輩、上司の方には知っておいて欲しいと思う「教える技術」を記事にしてみたいと思いました。
新人や長年いるのに成長しない部下など仕事において人が人に教える場面は数多くあると思います。
そんな時に部下や後輩をどんどん成長させる敏腕社員と実力は敏腕社員より上の評価なのに部下や後輩が育ってこない社員がいたりします。
その2者の違いは何なのか?
どのようにして部下や後輩を育てたらより早い成果に繋がるのか?
といった内容を数回くらいに分かれると思いますが自分の知識のある限りお伝え出来たらと思いました。
出来るプレイヤーが出来るマネージャーだとはかぎらない
優れた業績を上げてそのままその人が組織のリーダーに選ばれることは一般的に良くあることかと思います。
例えばもの凄いスピードで業務を熟し、新しいアイディアや意見をバンバン提案して「あいつはすごい!!」などと周りから評価されて意気揚々と管理職に就いた人のチームが思ったより業績が上がらないなんてことはざらです。
これはなぜなのか・・・
考えてみれば当たり前です。
だって業務を熟すのが他人より秀でてるんですから、自分以外の人に任せるより自分がやった方が早く確実に終わるんです。
優秀な人材が管理職になって最初に間違えるポイント
それがこれです!
確かに自分で何でもやれる方が早いし確実だし余計な時間かけなくて済みます。
しかし世の中の多くの仕事はチームで動きます。
自分だけどんだけ早く出来ようがチームが回らなければ業績は付いてきません。
業務で優秀な業績を上げてた人はそのことに気が付きにくいのです。
管理職でそのもどかしさを経験したことある人は結構いるのではないでしょうか?
そのもどかしさを解決するために必死に夜遅くまで一人残りチームの残った業務を行って疲弊していく有望な方。
上手くいかない理由を成長してないチームのせいにして必要以上に煽ってしまい時にはハラスメントとして会社にフィードバックされる方。
みんな一所懸命なんです!
知ってます!
ただ一所懸命の力の使い方を知らないんですよね。
「自分の仕事をこなす技術」と「人を育てる技術」はまったくの別物
これが良くわかるのがアスリートの世界です。
例えば、オリンピックで金メダルを獲得した素晴らしい成績を残した選手のコーチは超有名なスパースターだったでしょうか?
プレイヤーとしては中堅レベルだったけれど、メンバーの力を最大限に引き出すことや新人を育てることに長け、素晴らしい成績を上げる監督もいたりします。
話を戻しましょう。
ではなぜ、優れた業績を築いた人材であるにもかかわらず、部下を育てられないのか?
その理由は
「教え方を知らないから!」この1点につきます。
部下や後輩を指導・育成するには、その為「教え方」を学ぶ必要があるのです。
上でも書きましたが今年も新人の社員が入社されて来たでしょう。
その子達はある程度研修期間を経て配属するべき部署に・・・
ここから先の「現場の仕事の内奥をどう教えるか!」については、部下を受け持つ上司の手にすべて委ねられます。
そのため、もし上司が「教え方」を知らなければ、当然部下は会社の期待に応えられる社員には育っていきません。
「教える技術」を身につければ、人を育てることが楽しくなる!
日本の悪い風習だと僕は思っていますが、「仕事は細かく教えてもらうのではなく、盗んで覚えるものだ」的な考え方ってまだまだ残っていますよね。
これって上司や先輩が、教えることを放棄していることになります。
結局こういう上司や先輩から指導を受けた人は、良くわからないままなんとなく仕事をして良くわからないけどそれなりにやってる人か
自分で勉強したり努力して考えその上司や先輩よりも高い水準で仕事をする人になります。
後者になるのはなかなか難しかったり努力の方向を間違えると疲弊して精神を病んでしまったり、退職してしまったりします。
結局きちんとした教え方を受けてこなかった人はその経験を元に、自分の部下に対しても同じような指導しかできないのが当たり前なんです。
僕も初めて後輩や部下を持った時は自分のやっているところを2~3日見せて必要な個所を説明してあとはやれるね!
的な感じで教えているとも言えない指導を行っていました。
その後半年も経てば成長してない後輩や部下に頭を悩ませるなんて事を何年も繰り返していました(笑)
そこでインターネットや本などを読み漁りなんとか自分の部下を成長させる方法は無いか模索して集めた情報の結果がこれからお伝えする内容となっています。
僕自身まだまだ勉強途中ですが知る前と知った後では大きな差が感じられた事と、実際のチーム業績が伸びたり自分が教えていた部下が新人を期待以上に育てたりと効果も実感できましたので是非実践してみてください。
すべてのビジネスは行動の集積でできている
会社の売り上げ目標はそれぞれの事業部門や店舗によって振り分けられ、それをもとにそれぞれの社員の個人目標が決まります。
そして、各社員の頑張りは「目標を達成したか?」「いくら足りなかったか?」という結果によって判断される。
それが一般的なマネジメントになると思います。
もし、目標を達成できなかった人がいれば、「どうした?もっとがんばらなきゃダメじゃないか!」とげきが飛ばされます。
少し大げさですが大体こんな感じではないでしょうか?
では、このように目標の数字を決めて、それを達成できたかどうかという「結果」だけに着目していれば、確実に成果が上がるのでしょうか?社員は成長できるのでしょうか?
答えはNoですよね?
着目するべきは「結果」ではなく「行動」です。
なぜなら、物事の成果は、すべてその人の「行動」の積み重ねによって成り立っているからです。
ビジネスにおけるすべての結果は社員の「行動の集積」によるものなのです。
思ったような結果が得られないのなら、結果にいたるまでの社員の行動を変えてあげればいいことなのです。
やるべきことは、いたってシンプルです。
間違った行動をしているのなら、それを「望ましい行動(=成果に繋がる行動)」に変える。
成果に繋がる行動を実行していないのであれば、その行動を具体的に教えて実践させる。
「望ましい行動」が増えれば、結果は必ず改善されます。
どんな職場であっても「成果に繋がる、望ましい行動」は必ずあります。
それを繰り返し実践していけば、間違いなく結果に表れます。
「行動」に着目する。これこそが「教える」ということの最大のポイントです!
「いつ・誰が・どこで」やっても同じ結果が得られる
組織の中で部下にどういう事を望んでいるかというと「再現性」であると思います。
Aという商品を作るのにあの人なら5分でできる、あの子なら10分かかるけど高い品質のものが作れるでは現場の生産性と品質にバラつきが出てしまいます。
誰がやっても同じ時間で同じ品質のものが出来るこれが「再現性」です。
つまり「いつ・誰が・どこで」やっても同じ結果が得られるという事が理想なわけです。
次回からはこの再現性を再現するためにどんな技術が必要かということを書いていこうと思います。
部下や後輩の「行動」にフォーカスすることで、ストレスを感じたりイライラしたりすることもなくスムーズに仕事を教えられるだけでなく、これまで成長が見られなかった部下や後輩も、成果を上げられる人材へ育つお手伝いができたらと思います。