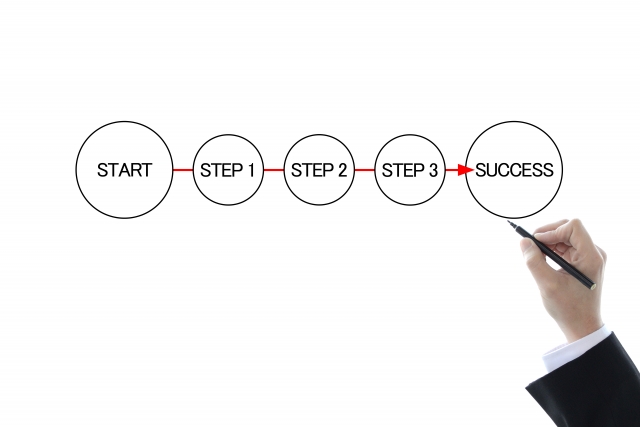
皆様こんにちは!
前回に引き続き「部下や後輩が成長しないのはあなたが教え方をしらないから」を話していこうと思います。
やはり思っていた以上のボリュームになりそうなので回数は複数回に分けて少しずつ更新していこうと思います。
ごめんなさい。。。
部下や後輩の成長に根性ややる気は関係ない!
僕たちは毎日のように「教える」という言葉を使っています。
人に何かを教えたり、人から何かを教わったりする機会もひんぱんにありますよね?
では、「教える」とは何をすること?と改めて質問されたら、すぐには答えられない方もいるのではないでしょうか?
もし、部下や後輩の教育や指導について「なんとかしたい」「もっとよくしたい」と考えているのなら、“「教える」とはなにか?”を一度真剣に考える必要があります。
「教える」とは、相手から”望ましい行動”を引き出す行為
僕は「教える」という言葉を、このように定義しています。
部下や後輩に「教える」ことによって、「望ましい行動」を引き出す。
例えばですが
会議室の場所を教える→(引き出される行動)=会議室までたどり着く
ゴミの分別ルールを教える→(引き出される行動)=ゴミをルール通り分別する
簡単な例ではありますが、人は「教える」ことによって相手を望ましい行動へと導けることがうかがえると思います。
さらに詳しく考えると、望ましい行動への導き方には2種類あると思います。
【タイプ1】
相手が”望ましい行動”を身につけていない場合
↓
”望ましい行動”をできるようにする
例えば、Aという作業の手順を知らない人に正しい手順を教えることや、初めて使うPCソフトの入力方法を教えることが、これに当たります。
【タイプ2】
相手が”間違った行動”をしている場合
↓
”望ましい行動”へと変える
例えば、資料を作成する際のフォントサイズが指定のサイズとは違うサイズで作成している人に正しいフォントサイズを教える。
といったことに当たると思います。
教えたことがちゃんとできない、仕事の覚えが悪い・・・。そんなとき、「仕事に対する熱意が足りないからだ!」というふうに、原因を部下や後輩の「心」のせいにしてしまう上司が少なくありません。
僕もそうでした(汗)
しかし、「教える」というのは「相手から”望ましい行動”を引き出す行為」ですので、注目すべきなのは「行動」です。
「根性」や「熱意」といった、気持ち=「心」にばかりこだわっていては、いつまでたっても問題は解決しません。
部下が仕事を覚えないのは、上司の「教え方」が適切でないために、望ましい行動が引き出せてないからだということをはっきりと認識しましょう。
「教える」にあたって大切なのは、部下の「行動」の観察・分析です。
・望ましい行動をしていないなら、その行動ができるまで教える
・行動が間違っていれば、それを正しい行動へ変えさせる
・望ましい行動が出来ているなら、その行動をさらに実行し続けさせる
日頃、その意味を深く追求することなく、なにげなくやっている「教える」という行為を、「行動」というキーワードに着目して見つめ直すと、上司のやるべきことがきっと見えてくるはずです。
部下の「根性」や「やる気」を正すのが、上司の仕事ではありません。
部下から「望ましい行動」を引き出すことこそが、上司がすべき「教育・育成・指導」なのです。
教える内容を事前に整理しておく
・教える内容を「知識」と「技術」に分ける
「教える」とは何か?その内容が明確になりましたね。
次に考えなければならないのは教える「内容」になります。
日頃皆さんは部下や後輩に業務を教えるとき、事前にその内容をきちんと整理しているでしょうか?
何の準備もなく、その場で頭に浮かんだことをランダムに教えるとう方法では、肝心なことが抜けてしまう危険性が高いですし、教えられる部下や後輩からすると、仕事の全体像が把握しにくくなってしまいます。
そのため、的確に効率良く教えるためには、事前の整理が必要になります。
仕事を教えるときに必ずやってほしいことが、教える内容を「知識」と「技術」に分類することです。
「知識」とは、聞かれたら答えられること。
「技術」とは、やろうとすればできること。
具体的なイメージとしては、自動車学校のカリキュラムが良いでしょう。
「学科教習」と「技能教習」にはっきりと分けていて、それによって教えられる側が、”今は知識を学ぶじかん””今日は技術を習得する日”というように意識し、効率よく学ぶことができます。
教える内容を「知識」と「技術」に分けることで、指導の内容や手順が整理できますし、もし指導が上手くいかないことがあっても「技術が未熟?それとも知識が不足?」と原因を見つけやすくすることができます。
”出来る社員”の「行動」を徹底分析する
「教える」という機会は、職場でも家庭でもさまざまな場所にあります。
しかしその対象をビジネスに限れば・・・
”部下や後輩が「望ましい行動(=成果に繋がる行動)」を行えるように導く”
これこそが、「教える」ことだと言えると思います。
答えの見つけ方は簡単で、チーム内の優秀な社員の仕事ぶりを観察すればいいだけです。
なぜなら、成果を出している人は成果の出る行動をしているからです。
仕事にはさまざまなやり方がありますから、複数の”優秀な社員”の仕事ぶりを観察・分析するのが理想的。
そうすることで、成果を出すために絶対欠かせない「行動」が浮き彫りになってきます。
もし、上司や先輩である皆さんがその業務に卓越しているのなら、皆さんがプレイヤー時代にしていた「行動」も合わせて分析してみて下さい。
こうして「成果に繋がる望ましい行動」を見つけ出し、それを一覧に書き出せば、その業務で成果を出すための「チェックリスト」が完成します。
リストに書かれている行動は、”成果を出している人の行動”なので、それを再現すれば、どんな人でも成果を上げられる可能性が大いに高まります。
優秀な社員の行動を観察し、チェックリストを完成させるには手間がかかりますが、一度つくっておけば、この先他の部下や後輩を指導する際にもそのまま活用できます。
部下の「出来ること」「知っていること」をチェックする
次にやるべきことは、部下や後輩がその業務について「どこまで知っているか?」「どこまでできているのか?」を確認します。
「こんなことは当然知っているはず」という思い込みは厳禁です。
新人はもちろん、中途社員や他部署から異動してきた社員についても、入念なチェックが必要になります。
「知識」のチェックは一問一答形式のテストが最適です。
質問事項は業務で必要な専門用語、成果を出すための重要ポイントなど。できる社員の行動をもとにつくった「チェックリスト」に沿って割り出していきます。
「資材Aの3つの特徴は?」「商品の追加発注はどこへ連絡する?」といったことを、口頭あるいは記述で回答させていきます。
一方の「技術」は実際にやってもらえばいいだけです。
・実際にAという商品を作ってもらう。
・この機械の操作を実際に行ってもらう
という具合です。
この2つのチェックを行うことで、その人が「知っている事」「出来ること」が把握できたら、チェックリストと比較します。
【成果を上げている人の行動(身につけている知識・技術)】と【部下の行動(身につけている知識・技術)】の間にあるギャップが【部下に教えるべき行動(部下に不足している知識・技術)】ということになります。
あとはそのギャップを埋めてあげる事が成果を上げる社員を育てる過程になります。
プライベートの話で信頼関係の土台づくり
・まずは上司から、仕事以外の話をしよう
仕事の指導やじんざいの育成を成功させるために欠かせないのは、教える側と教わる側との信頼関係です。
とくに、新入社員や新メンバーなど、これから仕事のパートナーとなる人と信頼関係を築く最初の段階では、”安心して仕事の話ができる土台づくり”が重要です。
ポイントは「最初から仕事の話をしてはいけない」ということ。
ではなんの話をするのか?
それはプライベートな話題です。
※コンプライアンスに注意して話をしましょう
部下、後輩と上司、先輩が人間的な側面を共有し合うことで、心おきなく仕事の話が出来るような関係性をつくりましょう。
まずは、上司先輩である皆さんから。例えば趣味の話、休日の過ごし方、好きな本や映画といったことでいいと思います。
こういう会話を繰りかえしていく内に、部下や後輩の緊張感はやわらぎ、自分の事を話しやすくなるはずです。
共通点が見つかれば、両者の距離はぐっと縮まるでしょうし、たとえ共通点が見つからなくても、お互いの親近感は間違いなく深まります。
「この人は信用できるかな?」「なんか近づき難い」と不安に思っている状態と、「漢字のいい人だな」「信頼できそうだ」といった安心感・親近感がある状態。今後の指導・育成がスムーズにいくのは、もちろん後者ですよね!
部下の働く理由を知る
かつての日本企業では、おそらくほとんどの社員が「出世して、たくさんお金を稼いで、マイホームやマイカーを買う事」などを目標に日々働いていたことでしょう(個人的な意見です。)
しかし、今ではその会社で働く理由は社員一人ひとり千差万別です。
”将来、起業するのに必要な資金や経験を積むため””趣味の活動にお金が必要。だから働いてる”などなどetc…
社員の数だけ、目標や仕事に対する価値観がある時代になっています。
「給料を上げたかったら、休日返上でがんばれ!」「男なら、奥さんをもらって養えるだけの力をつけなきゃダメだ!」なんて時代遅れのセリフでハッパをかけても、社員の心には全く響かないどころかブラック企業やパワハラのレッテルを貼られかねません。
たとえば、いずれ起業を考えている社員であれば「今度のプロジェクトは人脈を広げるチャンスだぞ」とアドバイスすれば、仕事への意欲も沸くかもしれません。
趣味を大切にしている部下なら、”ノー残業”を成功報酬にすることで、より積極的に仕事に取組み、目標達成につながるかもしれません。
是非、部下や後輩とフランクに話をして「仕事を通じて何を得たいのか」「人生における目標は?」「なぜ今の仕事を選んだのか」といったことに対する思いを引き出してください。
その積み重ねが人と人との信頼関係をより大きくしていくことになると思います。
部下の悩みを「聞く」
皆さんは、日頃あまり会話や交流のない上司や先輩に悩みを相談したり、本音を打ち明けたりしますか?
おそらくほとんどの方が「NO」だと思います。
普段から話を聞いてくれる相手だからこそ素直に話ができるし、何かあれば相談にのってもらいたいと思うものですよね。
部下や後輩に悩みやミスの情報をいち早く話してもらいたいなら、上司のあなたは”部下の話をしっかり聞く習慣”を身につけなければなりません。
なぜ、上司に話してくれないのか?答えは簡単。上司がしゃべり過ぎてしまうからです。
「実は今日、取引先で・・・」と途中まで聞くと、それをさえぎって「それは、こうすればいいんだ」と自分の経験をもとに話し始めてしまう。
日頃から部下に十分話をさせ、それをしっかり聞く習慣を持たなければ、その奥にある本音や悩みを引き出すことはできないですよね。
部下の話を聞くときには、徹底的に聞き役に徹することが大切です。
ここまで読んで頂いてありがとうございます。
まだまだ深堀り出来る内容なので次回以降もう少し深掘りしていこうかと思います。
教える技術からさらに成長するために「伝え方」や「褒め方」など書かせてもらおうと思っています。
僕自身まだまだ出来てないことだらけで、この内容を皆さんと一緒に勉強していくつもりで書かせてもらっています。
ではまた次回☆彡