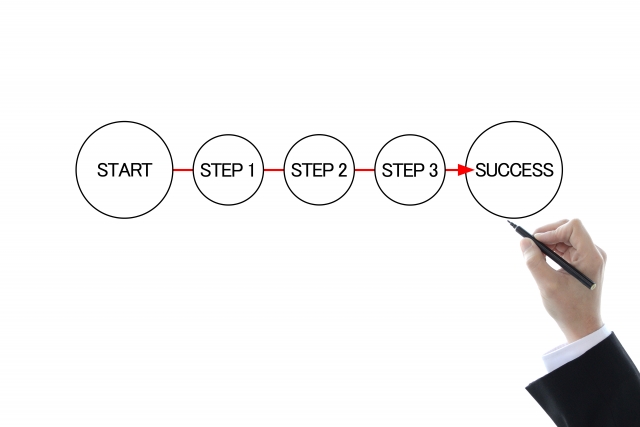
こんにちは!前回に引き続き部下や後輩が成長しないのはあなたが教え方をしらないから第三回目になります。
前回までの内容でほぼほぼ実践に活用できる部分まで説明できていると思います。
今回からはさらに部下や後輩が、より効率的に成長するために考えるべきポイントなどを説明していきたいと思います。
「わかりました!」を当てにしない
・教えたらその都度確認しましょう
僕が仕事上で感じていることなのですが、何か説明や指導を行った後確認の意味も込めて「理解できた?」「不明点とかある?」など聞いてみると大体98%くらいの人が「わかりました!」と回答するように思います。
しかし、実際教えたことをやってもらうと結果は全然わかっていないことなんてざらにあります。
きちんと理解した上での「わかりました!」なら問題はないと思います。
実際は
・実はわかっていないけれど、「わかりません」と言いづらい
・本人はわかったつもりでいたが、間違った理解をしている
・わかったのかわかってないのか、本人がわかっていない
こんなケースが現実多いのです。
どんなに一所懸命教えたつもりでも、実際にわかっていないのであれば、その指導や教育は失敗です。
何かを教えたら、そのつど「本当に理解したのか?」「本当に身についたのか?」確認することを習慣にしましょう。
僕の実践している方法は3つあります。
①復唱させる
教えた「知識」がどれだけ伝わったかを確認する、もっともシンプルな方法ですね。
最初に「最後に復唱してもらうので、しっかり聞いておいてね」など伝えておけば、より集中して聞いてくれるようになると思います。
「知識」ではなく「技術」を教えた場合は、自分の手本通りに部下や後輩が実演できるか確認すればOKです。
前回説明したチェックリストなどをつかってどこまで理解できたかを確認していけばいいでしょう。
②レポートをかかせる
指導を受けて「わかったこと・学んだこと」を書かせます。
復唱させることよりも、多くの手間と時間を使用しますが、部下や後輩はその内容についてより深く考えることができますし、上司は自分の教え方が的確だったかどうかを冷静に評価できます。
そのため、出来上がったレポートはしっかりとチェックする必要があります。
チェックリストを基に、必ず伝わっていなければならないポイントをピックアップしておき、「レポートの中で、このうち8割以上のポイントについて書いてあればOK」というように合格基準を設定しておくのがおすすめです。
③成功パターン・失敗パターンを考えさせる
3つめは「教えたことが、ちゃんとわかったかどうか?」が確認できると共に、学んだ事を仕事に生かす助けになるような方法です。
シンプルですが答える部下や後輩にはすこし勇気のいる内容かと思います。
教えた内容を「自分の仕事の中でどのような場面でどのように活用するか?」を部下や後輩自身に説明させる方法です。
これは答える側は聞く側の創造以上に怖い質問になります。(特に新人)
そのことを十分理解したうえで、正解でも不正解でもポジティブなフィードバックを心がけましょう。
「わかる」と「できる(学んだことを仕事で使いこなす)」の間には、とても大きな隔たりが存在しています。
”頭では理解していたのに、実際の現場ではうまく活用できなかった”なんて経験、きっと皆さんもあるはずです。
その為のトレーニングになるのがこの方法です。
重要なのは、ただ漠然とイメージさせるのではなく”成功パターン”と”失敗パターン”に着目させることです。
教えたことを「仕事で生かす場合、どうすれば成功する?」「どうしたら失敗に繋がってしまう?」
という両方について、そのポイントと理由を説明させることが、”成功のイメージ”と”やってはいけないこと”をはっきり言葉にさせることで、「わかる」から「できる」への移行が、なにもしないときよりも格段にスムーズになるはずです。
指示や指導も”具体的な行動”で表すこと
業績目標などで、「売上を伸ばす」「商品知識を増やす」「チーム力を上げる」など、こんな目標を掲げていることありませんか?
なんとなく伝わりますが、これでは業績アップや目標達成はなかなか望めません。
なぜなら表現が抽象的だから。具体的にどんな行動をすればいいのか解らないのですから、努力するのが難しくなります。
目標達成のために実践すべき行動を具体的に表現する。これもリーダーの仕事です。
行動を具体的に言語化するとき、参考になるのが「MORSの法則(具体性の法則)」です。
MORSの法則
・Measured 計測できる(=数値化できるという意味)
・Observable 観察できる(=誰が見ても、どんな行動をしているのかわかる)
・Reliable 信頼できる(=どんな人が見ても、それが同じ行動だと確認できる)
・Specific 明確化されている(=何をどうするかが明確になっている)
この4つの条件を満たしていないものは「行動」とは呼べないと定義されます。
改めて、上記の目標を見てみましょう。
・売上を伸ばす
・商品知識を増やす
・チーム力を上げる
どうでしょうか?どれも一見「行動」を表してるような印象ですが、4つの条件をどれもクリアしていないので、これらは「行動」とは呼べないのです。
MORSの法則を基に書き換えてみると・・・
・売上を伸ばす→1日10人のお客様におすすめの商品を案内する
・商品知識をつける→毎日3商品分の社内資料を読み込む
・チーム力を上げる→一緒にシフトに入る全スタッフは業務前に声を掛ける
やるべき行動をこのように具体的に書き出せば、社員それぞれが実行できているかどうかがはっきりわかります。
もしできてない人がいた場合でも、指導すべきことが非常に明確です。
また、成果が思うように上がらなかった場合も「回数を倍に増やす」「こういう行動を加える」というように、具体的な検討が可能になります。
目標だけでなく、指示などもこのMORSの法則に当てはめて考えていくと具体的な行動が見えてきます。
・計画書をできるだけ早く提出して」とかの場合
↓
明日の午前11時までに、僕のメールに添付して送ってください。
このような感じで具体的な行動を指示してあげるだけで行き違いなどは起こらなくなってきます。
皆さんも是非実践してみてください。
大きな目標を達成するためには
・スモールゴール(小さな目標)でたくさんの成功体験を!
ビジネスの売り上げ目標はもちろんですが、たとえば”3000m級の山を登る””フルマラソンで完走できる体力をつける”など、大きな目標、長期的な目標を確実に達成するためにおすすめなのが、スモールゴール(小さな目標)です。
マラソンの例で言えば「一週間の走行距離の合計を、毎週2㌔ずつ増やす」とかになります。
スモールゴールを設ける最大の理由は達成感です。
たとえどんな小さな目標でも、それをクリアできたという「達成感」が生まれ、その成功体験は、さらなる努力を続けるための原動力になります。
しかも、一つのスモールゴールをクリアしていけば、必ず大きなゴール(最終目標)に確実に近づいていく事になります。
注意することとしては、スモールゴールの設定は、あくまでも”達成感を味合わせる”ことが目的なので、ハードルを上げすぎないことが肝心です。
”ちょっとがんばれば出来る”という程度の難易度が理想的です。
上司と部下が一緒に相談してスモールゴールを設定しましょう。部下がスモールゴールを着実にクリアできているか、上司が定期的にチェックし、達成出来たら評価するというのが理想だと思います。
スモールゴールについても、出来るだけ数値を交え、「何をすればいいのか」が具体的にわかり、「できたか?できなかったか?」が明確に判断できるようなものにしていくといいでしょう。
一度にたくさんのことを教えない
・指示や指導は一度に3つまで
優秀なリーダー・マネージャーに共通していることは、”部下に何か教えたり、指示を出したりするとき、決して欲張らない”ということです。
なぜなら、人は一度にたくさんのことを言われても受け止められないからです。
一度に伝えるのは”具体的な行動”で3つまで!
3つ以上は、記憶力が優れていない人でない限りは行動が混ざってしまったり、重要な部分を忘れてしまったりしてしまいます。
・やらないことリストをつくる
部下や後輩に物事を伝えるとき、多くの人はまず優先順位を決めますが、「劣後順位」を先に決めることが役に立ちます。
多くの業務から”やらなくてよいこと”を見つけ出し、それを明確にするのが「劣後順位」です。
「あなたに達成してほしい目標はこれです。そのためにはこれとこれをやってください。ですのでこれとこれは目標達成に関係無いので、やる必要はないです」
こんな感じで伝えてあげればいいかなと思います。
部下や後輩に確実に仕事をこなしてほしいなら、欲張らずに絞り込みましょう。
読んで頂いてありがとうございました。
いかがだったでしょうか?
今回はここまであと2回くらいでまとめきりたいと考えています。
次回もまたよろしくお願いします☆彡