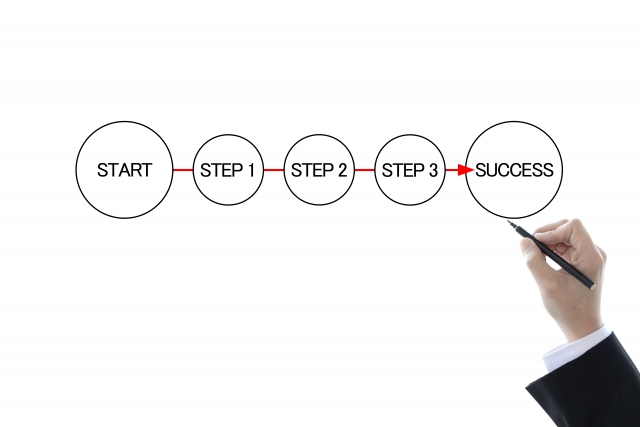
皆さんこんにちは今回も前回に引き続き教え方について書いていこうと思います。
前回まででほぼやるべきことは書いてきたかと思います。
今回は教え方を知ってさらにその後部下や後輩の成長をより促すサポートをどう行っていくかについて書いていこうかと思います。
部下の成長をサポートするために
・確実に100店が取れる課題で成功体験を
最近、自己評価が低く、自分に自信が持てない若者が増えているといわれています。
そこにはさまざまな原因があると思いますが、そのひとつが”人生における成功体験が非常に少ないこと”ではないかと僕は思います。
なんて言ってる僕自身もそんなに多くの成功体験なんて持っていませんが(汗)
成功した体験がないわけではないのです。僕も今の若者も・・・
問題なのは”凄く頑張った→成功した→認められた→うれしい”と、はっきり認識できる機会が少なかったんだと思います。
たぶんですが、子供同士の競争や順位づけを極端に排除した”ゆとり教育”がその一因ではないかと考えています。
僕が子供の頃はギリギリゆとり世代一歩手前だったので”小さな成功体験”を手にする機会がありました。
たとえば運動会のような行事の中や、休み時間の遊びの中にもあったと思います。
新人教育の早い段階でこうした達成感をたくさん持たせることは、本人にとって”やればできる”という大きな自信になっていくと思います。
そのうえで徐々に高いレベルの課題を与えていくのが良いサポートになると考えています。
解決のカギ?「ABCモデル」
ここまで教え方について色々説明してきましたが、重要なことが一つ残っています。
それは「知っている・できる」を「実際にビジネスの場で実践し続ける」というレベルに引き上げるということです。
僕たちは”仕事ができるようになってもらうため”に部下や後輩に仕事を教えますが、実は仕事の内容を「教える」だけでは不十分なのです。
なぜなら「知識を身につけた・できるようになった」ということと、「身につけた知識や技術を、日常業務の中で実際に活用し続けること」の間には大きな隔たりがあるからです。
例えばですが、誰でも”健康を維持するためには、日々の適度な運動が必要である”ということは知っています。
ウォーキングやストレッチなど”適度な運動”を技術としても知識としても知っていますよね?
しかし、これがなかなか続けられないですよね?(僕だけかな?)
部下や後輩に「知識」や「技術」を身につけさせることはもちろん大切ですが、部下が実際に実践し続けるようにサポートすることも必要不可欠なことなんです。
そこまでできて初めて、皆さんの「教える」というスキルが完成すると思います。
では、なぜ人はある「行動」を繰り返したり、やめたりするのでしょう?
これを論理的に説明してくれるのが「ABCモデル」という概念です。
ABCモデルは次の3つの要素から成り立っています。
A先行条件(Antecedent)・・・行動の直前の環境
↓
B行動(Behavior)・・・行動・言動・ふるまい
↓
C結果(Consequence)・・・行動した直後に起きた環境の変化
A=先行条件、B=行動、C=結果には明確な因果関係があります。
(A)先行条件によって(B)行動が引き起こされとき、得られた(C)結果が望ましいものであれば、それが(A)先行条件に影響を与えるので、再び(B)行動が引き起こされます。
つまり、(B)行動によってよい(C)結果が得られれば、その(B)行動は繰り返されます。
一方、(C)結果が望ましいものでなければ、人はその(B)行動を行わなくなります。
例
A先行条件「同僚にお菓子をすすめられた」
↓
B行動「一つ食べてみた」
↓
C結果1「とても美味しかった」
結果2「苦手な味だった」
極端な具体例ですがこうしてみると(C)結果のあとに「もう一つお菓子を食べる」か「もう食べない」かという(B)行動の選択肢が生まれてくるわけです。
このように、人は何かの行動によって直後に”望ましい結果”が得られると再び同じ行動を繰り返そうとします。
ですので、部下や後輩に実践し続けてほしい行動がある場合、このABCモデルの因果関係をコントロールしてあげると効果的になるといえます。
正しく「ほめる」ことで部下や後輩の成長・業績をアップさせる
・「行動」をほめるのは難しくない
上記に書いた「お菓子を食べる」という行動のように、直後に”望ましい結果1”が得られれば、人は「お菓子を食べる」という行動を繰り返します。
では、たとえば「痩せるために走る」という「行動」の場合どうでしょう?
もちろん毎日走り続ければ、いずれは痩せていきますが、それがわかっていても、なかなか続かない理由もABCモデルで説明できます。
その理由は、「行動」の直後に”望ましい結果”が得られないからです。
思い立って5㌔を走ったところで、当然ながらすぐには体重は落ちません。
それどころか、疲れる、足がいたい、横腹がいたい、というような望ましくない結果だけだけが先に起こります。
ビジネスでも”この行動を継続すれば、必ず売り上げが上がる”と頭では理解していても、すぐに”いい結果”が得られるわけではないので、続かない・・・。
そこで「行動」の直後に「望ましい結果」すなわち”ご褒美”を与えるというのがここでの考え方です。
例えば、5㌔のランニングを実行するたびに、何かご褒美がもらえるとしたらどうですか?
その褒美欲しさに、ランニングという「行動」を続けられる可能性は飛躍的にあがります。
何かの「行動」に対して”ご褒美”を与えることを、「強化」と呼び、「強化」することによって「行動」の頻度が増えることは、数多くの行動科学の実験によって立証されているそうです。
では、ビジネスマンにとって最高の”ご褒美(強化)”とはなんでしょうか?
答えは「上司から褒められること」「上司から認められること」です。
部下や後輩が”望ましい行動”をしていたら「よくやってるな。その調子だ!」といった声かけによって、褒めたり、認めたりする。
そうすることで、自分の行動が認められた部下や後輩は、また褒めてもらおうとして、その行動を繰り返します。
人を成長させるには褒めることが重要だというのは、科学的にも理にかなっていることなのです。
目的は、部下や後輩の”望ましい行動”に「ほめる」というご褒美を与えて、その行動を繰り返すようにサポートすることです。
「ほめる」という”ご褒美”が”望ましい行動”を再び繰り返す原動力になります。
逆に言えば、人間は”人から認めてもらえない行動は、続ける事がでできない”ということになります。
「叱る」際のポイント
・人格や性格を叱ることは×
部下や後輩に仕事を教えて、育てていく中で叱ることが必要な場面ももちろんあります。
その際にしてはいけないのが、「どうしていつもモタモタしてるんだ」「そういう性格だから売れないんだ」というように、人格や性格を叱ること。
あくまでも、焦点を絞るのはその人の「行動」です。
・やらなければならないのに、やらなかった行動
・やってはいけないのに、やってしまった行動
叱る対象はこうした「行動」だけにしましょう。
僕は色々間違えて気づいたら孤立してしまうなんて経験もしています(汗)
そして、叱った後は必ずフォローをしましょう。
フォローといっても”ご機嫌とり”にならないよう注意してください。
行動を望ましい方向へ変えていくために”キミに実行してほしいのは、こういう行動だ”と具体的な表現で説明し、場合によっては具体的な改善策やアイディアを与えてあげるとよいでしょう。
・誰がほめる(叱る)か?も重要
普段から自分の行動をきちんと評価してくれている上司から褒めれれば、その部下はますます積極的に仕事をするようになります。
またそんな上司であれば、叱られた場合も「自分の事を考えてくれているんだ」と素直かつ前向きに受け止めてくれるはずです。
気の利いたセリフで褒める必要はありません。
日頃から部下や後輩の様子に気を配り、”望ましい行動”をしていたら「僕はあなたのその行動を認めていますよ」という事を簡潔に伝えましょう。
 | 図解 教える技術 行動科学を使ってできる人が育つ! / 石田淳 【本】 価格:1,100円 |
いかがでしたでしょうか?
4回に渡って「教える技術」について説明してきましたが、あとは皆さまがこれを実践で活かしてチームの成長を促してあげるだけです。
是非この「教える技術」を使って、部下や後輩の成長の過程と皆様自身の成長の過程を楽しんで下さい。
ではまた次回☆彡